2021.3.5
【特集】東日本大震災からのスタートー IRIDeS研究者が復興と震災教訓の継承について話し合う(2)
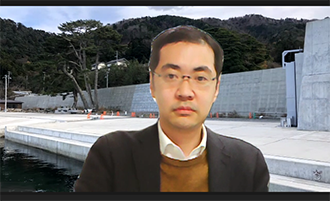
佐藤 大介 准教授
佐藤大:第26章「『民間所在史料』の救済」を川内淳史先生と共著で執筆しました。日本には推計で20億点を超える過去の文書記録があるという試算があります。そのほとんどは個人所有です。1995年阪神・淡路大震災を契機に、自然災害で貴重な資料を失わないよう、有志によるボランティア組織「資料ネット」が、被災資料のレスキュー活動を行ってきました。宮城県は、2003年7月に発生した地震を受けた活動が最初で、私も参加してきました。
東日本大震災により、かけがえのない人命、ふるさとの姿とともに、各地の資料が失われました。一方で、市民の方々と震災前から構築していたネットワークが生き、所蔵者に連絡を取り資料を救済できたケースも、私が関わった活動で83件ありました。また震災後10年で、延べ5,300人の市民ボランティアが水に濡れた資料の劣化を防ぐ作業に携わりました。

市民の資料保存活動の様子
(提供:佐藤 大介 准教授)
こういった活動は、災害後、何か役に立ちたいと思った市民の受け皿にもなりました。活動を通じて古文書に興味を持ち、自ら「くずし字」を学び、資料を解読して出版した方も現れました。資料保全活動は、歴史研究や資料救済を超え、被災者の心理・社会的支援にもなる可能性について、IRIDeS客員の上山先生やモリス先生が研究されています。何もかも失った被災者が、資料保全活動を通じて、200~300年単位の先祖代々の歴史を、自分の代で途切れさせずに再びつなげ、過去との関係を結びなおすことができるのです。
また、今回の被災地は、過去にも大災害を何度も経験していますが、資料は、携わった人々に過去の災害とそこから立ち直ってきた歴史を思い起こさせ、被災した地域と人々の回復も促すことがわかりました。普段から、市民・外部の人・専門家が一緒に地域の歴史に関わり実践的に活動することが、コミュニティを災害に強くする可能性を、この10年で実感しました。
マリ:歴史資料に精神的な影響があるのは興味深いです。ところで国際的に見て、伝承・古文書・語り部文化などは日本独特ですが、昔の人の伝え方は、今と同じなのでしょうか。
佐藤大:地域の中で自然災害が起こった際、過去の事例も振り返って古文書に記載されている事があるのですが、その日付は正確です。私も、誰がどのように語り継ぎ、社会のなかで記憶されていったのか気になっています。農林水産業や日々の生活の中で、人が集まる場面が多かったので、そこで繰り返し話題にされたのかもしれません。しかし、そのような場面は、記録には残されておらず、実態はわかりません。農林水産業や、そこからの産物を取り引きして暮らしていた江戸時代の人々にとって、自然災害はリスク要因である一方、商機をもたらす面もありました。いずれにせよ、その情報は生存に直結したのでしょう。語り部に関するご指摘については、心に留めてまた勉強したいと思います。
佐藤翔:IRIDeSに歴史資料保全分野がある意味は大きいのでしょうか。
佐藤大:日常的に違う分野の専門家と交流し、IRIDeSの来訪者に歴史の活動を知っていただく環境があることに、大きな意義を感じています。先ほどの語り部の話もそうですが、IRIDeSで刺激を受け、江戸時代以降の新しい時代の歴史も学び、いろいろ研究していきたいと思っています。
丸谷:今後、例えばIRIDeSのハザードマップの有効化の研究とリンクさせ、事前防災で、災害リスクの高い所の資料を重点的に撮影しデジタル化する活動があってもいいのではないでしょうか。
佐藤大:2003~2010年、まさに予防的活動で、古文書資料を片っ端からデジタル撮影していました。東日本大震災で原本がなくなり、写真だけが残った実例もあります。しかし、地域の古文書はとにかく数が多く、デジタル化も整理も手が回らないのが問題です。資料の所蔵者に事前に適切に災害リスクを伝え、所蔵者や地域の方々とともに資料を守るという発想も必要でしょう。
